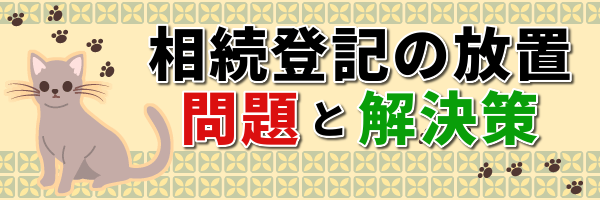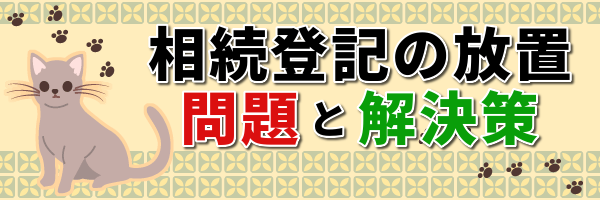東村山市・小平市・東大和市・東久留米市で
相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
成年後見の相談申立ては
東村山司法書士事務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
グランデール久米川part1 201号室(久米川駅から徒歩2分)
最初のご相談は無料です
(土日祝日は有料です)
当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
事前予約で業務時間外や土日祝も対応いたします。
贈与(生前贈与)による不動産の名義変更の費用
はじめに
1.司法書士にかかる報酬は一律ではありません
昔は,司法書士には報酬基準表があったため,皆その基準に従っていました。しかし,平成14年にこの基準が廃止されたため,現在では自由に報酬を決めることができるようになりました。
しかし,自由に決めることができても,各事務所は報酬基準を定めなければなりません。
司法書士は,不動産登記(相続登記)・商業登記などの登記業務だけでなく,遺言書の作成,裁判業務など多様な業務を行いますが,その中で,税金・郵送費・着手金・報酬などが生じます。
司法書士は,費用についての説明をする義務がありますので,事前に『いくらかかるのか』『いつ支払う必要があるのか』等について問い合わせてみましょう。
2.事務員が多い事務所・大きな事務所は費用が安い?
事務員の人数が多く,仕事を大量に受けている事務所であれば,費用も安い,と考えておられる方がいらっしゃいます。工業製品の大量生産や仕入れなどであればコストダウンが可能でしょうが,相続手続きや裁判手続きなどは,1件1件の問題や相談内容は当然に異るため効率化を図ることは困難です。
司法書士事務所や弁護士事務所などで一番かかるコストは「人件費」です。多くの事件を処理するためには当然多くの人手が必要となります。
したがって,事務員が多い事務所の方が人件費がかかるため,報酬を高く設定している場合もあるのです。
3.司法書士を選ぶ場合は慎重に
事務所選びは,相談の段階から,しっかり司法書士が直接対応しているか,が重要です。
大手の中には,電話をしてもいつも資格を有する者が出てこない,という事務所もあります。
また,無理に信託(民事信託・商事信託)や,ご相談者が求めていない遺産整理手続などを勧めてくる事務所には注意してください。相談者よりも,提携している信託会社や事務所の利益のために勧誘している可能性があります。あらゆる解決方法や可能性をすべて提示された後に,選択するのはあくまでご相談者でなければなりません。
手続にかかる費用は,多くの相談者の方の最も関心のある事柄だと思いますが,一番重要なことは,信頼できるかどうかだと思います。
贈与による不動産の名義変更(所有権移転登記)の費用
(以下は,すべて税抜き価格です)
相談料
| 初回の相談 | 0円 |
|---|
- ご依頼いただいた場合,同一事案については,手続き終了まで相談は無料です。
- 初回の無料相談は,30分ほどでお願いしております。
贈与による不動産の名義変更(所有権移転登記)の費用の目安
| 登録免許税(法務局へ支払う税金)(国税) | 不動産の評価額×1000分の20 |
|---|
- 例えば,不動産の評価額が1000万円の場合20万円が登録免許税となります。
- 国税としての税金ですので司法書士の手数料(報酬)ではありません。
- 評価額は,毎年送られてくる固定資産納税通知書に記載されています。また,市役所等で名寄せ帳などを取得されてもそれに記載されています。名寄せや評価の取得も行っております。
| 登記申請1件 | 不動産の数や複数管轄,評価額などで異なります。 |
|---|
- 複数の不動産があっても,全て同じ管轄の法務局であれば,1件で手続きできます。
- 管轄の法務局が異なると,法律上,別個に申請しなければなりません。例えば,2つの不動産が,宮崎地方法務局管轄と日南支局管轄で別々の場合,贈与登記申請も2ヵ所の法務局に申請が必要となり,合計2件となります。
| 贈与税(国税) | (贈与財産-110万円)× 税率 - 控除額 |
|---|
- 不動産の評価額,土地,建物,路線価での評価,倍率方式での評価などで異なります。
- 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に,税務署へ申告と納税が必要となります。
- 信頼できる税理士をご紹介しており,税金面でも安心してご依頼いただいております。
- 20歳以上の者が,直系尊属から贈与を受けた場合,特例贈与として税率の優遇があります。
- 「相続時精算課税制度」を利用すれば,2,500万円までは,贈与税は非課税で不動産の名義変更(所有権移転登記)が行えます。60歳以上の直系尊属(祖父母・父母)から20歳以上の直系卑属(子・孫)への贈与で利用できます。
| 不動産取得税(地方税) | 4% |
|---|
- 都税・県税になります。自治体によって特例の要件等が異なります。
- 中古住宅取得等の要件に該当すれば,減税措置が受けられます。
| 住民票・名寄帳兼課税台帳・評価証明書等の取得 | 取得通数で計算致します |
|---|
- お仕事で時間が無い方のために,私が全て書面を集めることも行っています。
- 取得枚数によって加算されます。
| 前提としての住所変更登記・氏名変更登記 | 内容により異なります |
|---|
- 贈与者(あげる方)の住所や氏名が,登記簿上のものと異なっている場合,贈与による不動産の名義変更の前提として,住所変更登記や氏名変更登記が必ず必要となります。
- 結婚等で氏名が変わられていたり,引っ越しで住所が変わられている場合などです。
| 登記事項証明書取得 | 500円(実費) |
|---|
| 登記情報取得 | 332円(実費) |
|---|
「相続時精算課税制度」の利用で2,500万円まで贈与税は非課税
| 要件 | 60歳以上の父母(祖父母)から20歳以上の子(孫)への贈与 |
|---|
| 非課税額 | 2,500万円 |
|---|
1.暦年課税制度と相続時精算課税制度(生前贈与における話)
暦年課税制度とは,相続時精算課税制度を選択しかった場合に適用される制度で,原則として適用されている制度です。「暦年贈与」という言葉を聞かれたことがあると思いますが,これは暦年課税制度が適用される贈与のことになります。
暦年課税制度での贈与税の計算は,その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によって取得した財産の合計額にみなし贈与財産価額を合計し,非課税財産を控除した額を課税価格とします。この課税価格から配偶者控除額と基礎控除額(110万円)を差し引いた残額に贈与税率を適用し,下記の速算表の控除額を差し引いて計算します。
暦年贈与の場合,相続時精算課税制度とは異なり,基礎控除額(110万円)は財産を渡す人を基準にするのではなく,もらう人を基準にするため,1年間に複数の人から贈与を受けた場合の基礎控除額は,贈与者の人数に関わらず贈与を受けた人ごとに110万円となります。例えば,ABCの3人から100万円ずつ贈与を受けた場合の基礎控除額は110万円となります。
なお,特例贈与財産とは,父母や祖父母など,直系尊属からの贈与により,受像年の1月1日において20歳以上のものが受ける財産をいいます。一般贈与財産とは特例贈与財産以外をいいます。
また、贈与税の申告は,贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行います。
相続時精算課税制度とは,60歳以上の父母又は祖父母から,20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し,財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。合計2,500万円までは非課税で,越えた部分について一律20%の税率で納税し,贈与者の死亡による相続税の申告において税額を精算します。年齢は贈与年の1月1日現在において判断します。贈与税の先延ばしともいえる制度です。
暦年課税制度とは異なり,財産を受け取る人を基準とするのではなく,渡す人を基準とします。例えば,甲と妻乙の間に推定相続人である子A1人がいるとすると,Aは甲から貰う財産で2,500万円まで非課税,乙から貰う財産で2,500万円まで非課税となります。
この相続時精算課税制度は,死亡による相続税の申告において精算すると述べましたが,例えば,1年目に1,000万円,2年目に1,000万円,3年目に800万円の贈与を受けた場合,非課税の2,500万円を超過する300万円について税率20%で課税されます。そして,その納税した額については,結局死亡後の相続税の計算において基礎控除以下で課税されなければ還付されることになります。
2.相続時精算課税制度を利用する際の注意点
(1)相続時精算課税制度の利用の届出
この制度は,利用することを選択した最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の税務署に,相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。届出書を提出しなければ暦年贈与が適用されるため注意が必要です。
(2)後から暦年課税制度に変更はできない
相続時精算課税制度を選択すると以後は暦年贈与制度に変更することはできず,贈与者が亡くなるまで続きます。
(3)毎年の申告
相続時精算課税制度を選択した以後は,贈与を受けた年ごとに申告が必要となります。したがって,贈与を受けていない年は申告の必要はありません。
(4)相続時精算課税制度を利用した場合の相続税の算出方法
相続時精算課税制度を利用した場合の相続税の算出は,相続(遺贈)により取得した財産の価額と,相続時精算課税の適用を受けた全贈与財産の贈与時点での課税価格との合計額で,相続税を算出し,相続時精算課税による贈与税額を控除して行います。
(5)相続時精算課税制度を利用した場合の相続税の負担割合
贈与者の死亡時点で,相続時精算課税制度を利用してもらい受けた財産(α)と,遺産(β)の全部を合計して相続税額を算出し,相続人がもらい受けたα+βの額の割合で負担します。
(6)相続時精算課税制度を利用した場合の贈与者死亡による届出等
相続時精算課税制度を利用した場合に,贈与者が死亡したタイミングで,税務署に対し,相続時精算課税制度を利用していた事や,贈与者が死亡した事実を届け出る必要があるのかが問題となりますが,基本的には何かを届け出る必要はなく,相続税が課税されるのであれば相続税の申告をすればよいことになります(その中で相続時精算課税制度の利用が前提となるわけです)。相続税も課税されない場合は何もする必要はありません。ただ,贈与税申告時に納税が発生している場合は,相続税の還付申告が必要になるため,その点は注意が必要です。
(7)贈与税の申告期限前に受贈者が死亡した場合
[平成31年4月1日現在法令等]
贈与により財産を取得した者が、相続時精算課税の適用を受けることができる場合に、その贈与を受けた年の翌年の3月15日以前に死亡し、「相続時精算課税選択届出書」を提出していなかったときは、その者の相続人はその死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付してその死亡した者の納税地の所轄税務署に提出することができます。これにより、その贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けることができます。
なお、この届出書には、次の書類を添付しなければなりません。
・相続時精算課税選択届出書付表
・受贈者の相続人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、受贈者の全ての相続人を明らか
にする書類
- ・受贈者の戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写しその他の書類で次の内容を証する
- 書類
-
- イ 受贈者の氏名、生年月日、死亡年月日
- ロ 受贈者が20歳に達した時以後死亡の日までの住所又は居所(受贈者の平成15年1月1日以後死亡の時までの住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
- (令和2年1月1日以後の贈与については不要)
- ハ 受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること
- ・ 贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証
- する書類(令和2年1月1日以後の贈与については不要)
- イ 贈与者の氏名、生年月日
- ロ 贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
- 注1 相続人が2人以上いる場合には、相続人全員が「相続時精算課税選択届出書付表」に連署しなければ、相続時精算課税の適用を受けることはできません。
- 注2 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。
(8)贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
[平成31年4月1日現在法令等]
贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合に、相続時精算課税の適用を受けるときは、贈与税の申告書を提出する必要はありませんが、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。この場合における「相続時精算課税選択届出書」の提出期限及び提出先は通常の場合とは異なり、次の 又は
又は のいずれか早い日までに、贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出します。
のいずれか早い日までに、贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出します。
 贈与税の申告書の提出期限(通常は、贈与を受けた年の翌年の3月15日)
贈与税の申告書の提出期限(通常は、贈与を受けた年の翌年の3月15日) 贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(通常は、相続の開始の日の翌日から10
贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(通常は、相続の開始の日の翌日から10- か月を経過する日)
なお、 の日がこの届出書の提出期限となる場合に、贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出するときには、相続税の申告書にこの届出書を添付しなければなりません。
の日がこの届出書の提出期限となる場合に、贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出するときには、相続税の申告書にこの届出書を添付しなければなりません。
- (注) 相続税の申告書を提出する必要がない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けるためには、提出期限までにこの届出書を贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、「相続時精算課税選択届出書」には、次の書類を添付することとされています。
- 1 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
- イ 受贈者の氏名、生年月日
- ロ 受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること
- 2 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所
- を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えあ
- りません。)
- ※ 平成7年1月2日以前に生まれた方が、令和2年1月1日前の贈与について相続時精算課税選択届出書を提出する場合に限ります。
- 3 贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証
- する書類 (令和2年1月1日以後の贈与については不要です。)
- イ 贈与者の氏名、生年月日
- ロ 贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
- (注) 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。
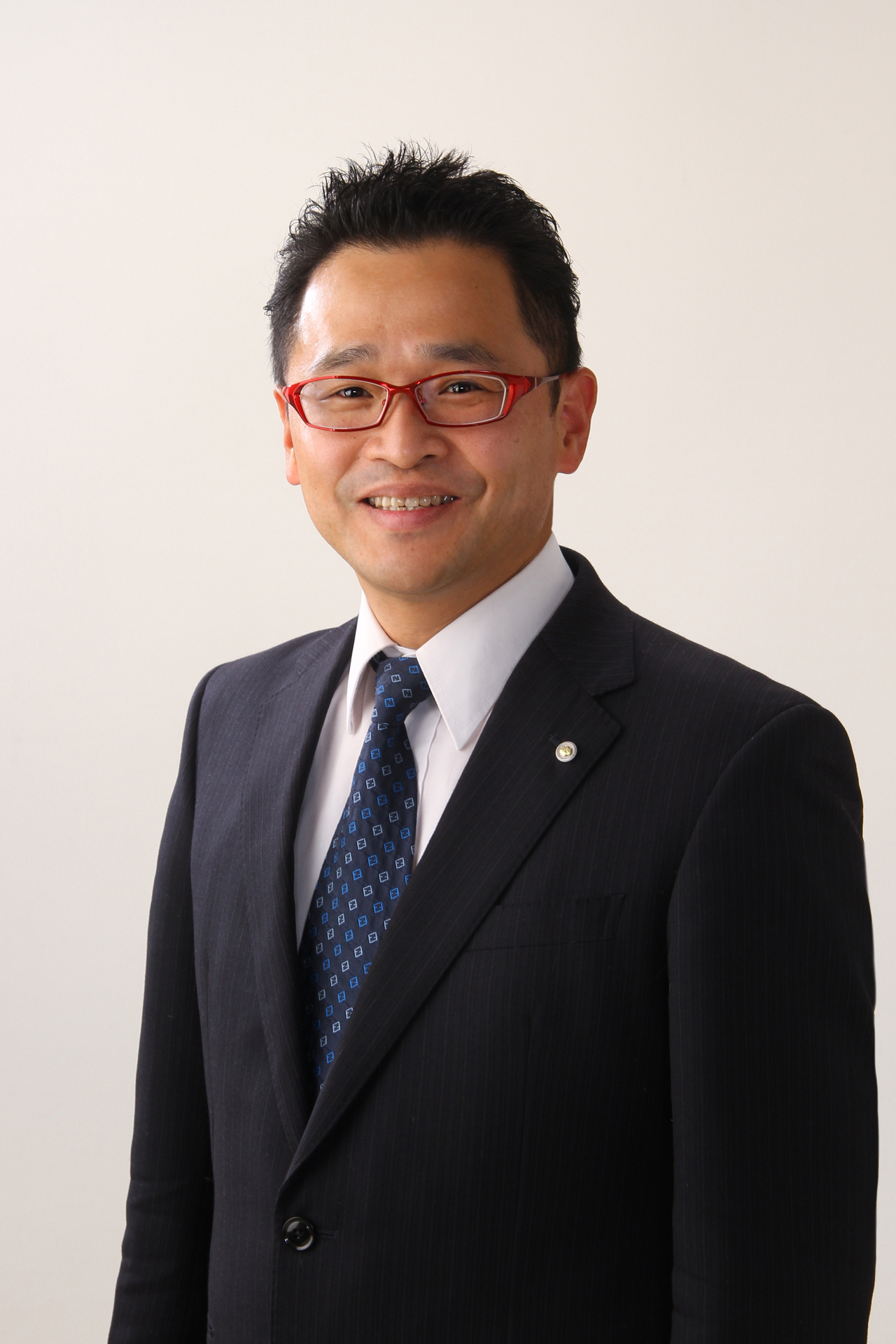
司法書士の
山田です

- 最初のご相談は無料です(30分程度)。土日祝日は有料となります。
- 当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。『大切な遺産や相続関係を安全に守るため』、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
| 受付時間 | 10:00~17:00 |
|---|
| 業務時間 | 9:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 土日祝日。事前の予約で,業務時間外や土日祝日でも対応いたします。 |
|---|
お気軽にご連絡ください。
==============================
最初のご相談は無料。土日祝日は有料。
※当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
「大切な遺産や相続関係を安全に守る為」、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
==============================